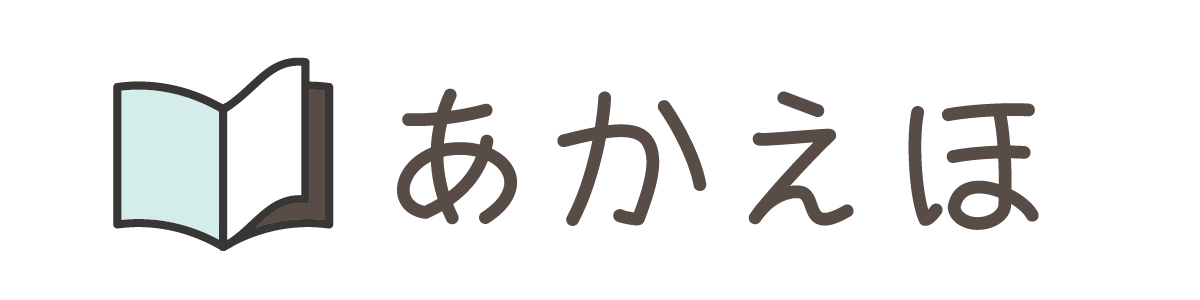『えんとつ町のプペル』という絵本をご存知でしょうか?
キングコングの西野亮廣さんと絵本の制作チームが手掛けた絵本で、ウェブ上で全ページ無料公開して大変話題に(というか大炎上)なりました。
私もウェブ絵本を読んでみました。子供の読み聞かせにどうかな?って思って。
私の中で、当時3歳の子供に読み聞かせるにはちょっと難しいかな~??という感想で、書籍の購入は見送ったのですが。
せっかくウェブ絵本を読んだので、私が感じたことを書いてみたいと思います。
ストーリーついて思うこと
ネットで全ページ無料公開されていますので、あらすじはここでは書きません。
でも、感想を書く上でどうしてもストーリーに触れる必要があります。
ぜひ絵本をご覧になってからこのブログの続きを読んでください。
どこかで読んだような?既視感のあるストーリー
「えんとつ町」という名の通り、舞台はえんとつだらけの町。しかも4000メートルの崖に囲まれている。
空は煙でおおわれ、人々は空の青さも輝く星も知らない。
西野さんはあとがきの中で、この町についてこう語っています。
えんとつ町は、夢を語れば笑われて、行動すれば叩かれる、現代社会の風刺
なるほど。
てか、待って、4000メートルの崖って?富士山よりも高い、山ではなく「崖」。
『進撃の巨人』 の壁の比ではないぞ・・・。
『えんとつ町のプペル』を読み進めてみると、海が存在したり、どんな地形なのかを想像するのが難しい・・・。
非常に閉鎖的で息苦しい世界であることを表現したかったのかな?と思いました。
また、えんとつの煙で空が見えない。
私は最初、人間の愚かさが招いた環境破壊がテーマかな?という印象を受けました。
『えんとつ町のプペル』は、ゴミの塊にひょんなことから心臓が宿って、「ゴミ人間」となったプペルと、プペルに心を許す少年、ルビッチの物語。
ルビッチは、プペルにどこか懐かしいにおいを感じて、死んでしまった父親の思い出話を語ります。
- 父親の写真が入ったペンダントをなくしてしまったこと
- えんとつ町では見ることができない空に光り輝く星がある、と教えてくれたこと
- 星の存在を町の誰も信じてくれず嘘つき呼ばわりされて死んでしまったこと
・・・あれ?なんかラピュタみたい。
ストーリーの展開、エピソードの端々にどことなく既視感があるような気がしました。
ただ、そのことを批判するつもりは全くなく。
新しい物語を作ろうとするときに、元ネタとなるストーリーがあったり、好きな話に影響を受けて似た雰囲気になったりすることはよくある。
絵本のように短い文章の中で伝えたいことを詰め込むためには、ある程度見聞きしたことのある展開をストーリーに組み込むのはアリだと思います。
『えんとつ町のプペル』が伝えたかったことを考察
「信じる心」と「愛」、でしょうか・・・。
閉鎖的環境、弱者差別、家族愛、信念、思いやり。
いろいろな要素があり、絵本としてはボリューミー。文字数が非常に多いので、テーマを見失いそうになりますが。
軸の部分は、「信じる心」と「愛」なのかな、と思います。
なんかね、私は読んでる途中で心が痛くなっちゃって。
心が痛いシーンのボリュームがすごいから、なんだかお腹いっぱいになってしまって。
ラストにあまり感動できなかった・・・。
この絵本を好きな人は大好きみたいだし、子供にも人気あるみたい。以前西野さん本人の発信を見た限りでは。
私はウェブ上でしか読んでないから、ちゃんと買った「絵本」で読んだら、印象は違うと思います。
挿絵はハイクオリティ。好みは分かれるかも
『えんとつ町のプペル』は税別2000円。
・・・結構いい値段しますよね!(^^;
その理由のひとつとして、挿絵の色にこだわり、通常の本の印刷では使わない特殊な色のインクを使用しているとか。
挿絵は複数のイラストレーターさんが手掛けています。
実際の絵本を手に取ったことはないですが、1枚1枚、本当に丁寧に書き込まれています。
画集みたい。


絵本の挿絵は西野さんの意向で、ブログなどで自由に使うことが許可されています。
絵のテイストはどこか外国風で、好みは分かれるんじゃないでしょうか。
また、舞台や人物の顔が海外のイメージなのに、ちょうちんがあったり、日本語の看板があったり。
面白いと感じるか、はたまたチグハグだと感じるか。
『えんとつ町のプペル』はロングセラーになれるか?見守りたいと思います(最後に)
『えんとつ町のプペル』は、ウェブで無料公開し、賛否両論の大きな話題になりました。
結果的には、当時、Amazonや楽天の絵本部門で売り上げナンバー1に!
ベストセラーとなりました。
でも、「絵本はベストセラーよりもロングセラーの物を選べ」と、そんな話も聞きます。
愛され続ける絵本は、子供の心を掴んでいるからこそ売れ続ける、という考えですね。
長く人々から愛され続ける絵本となることを願っています。