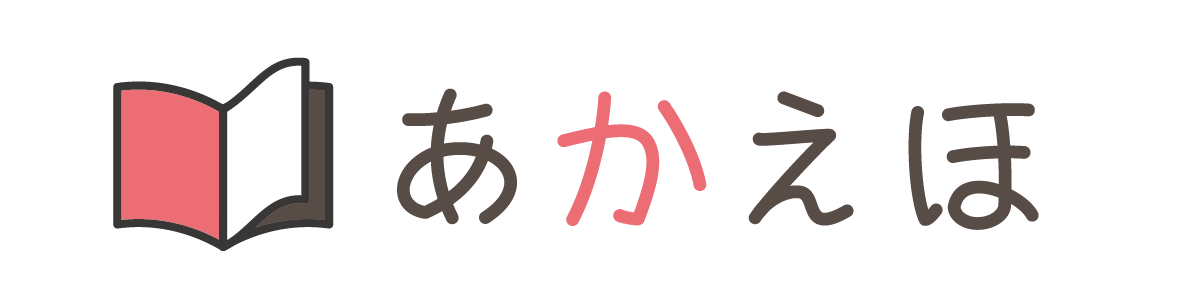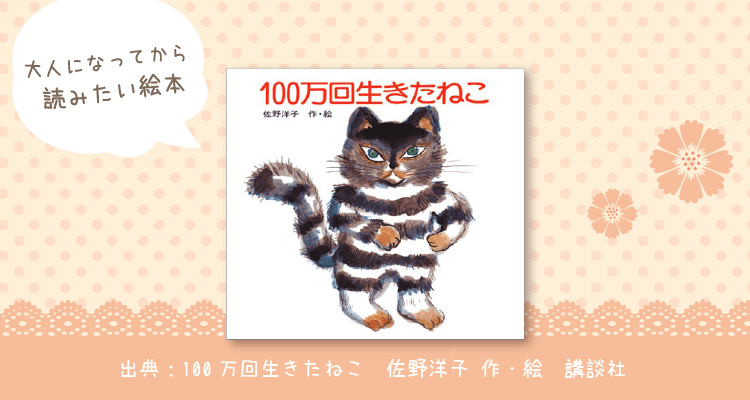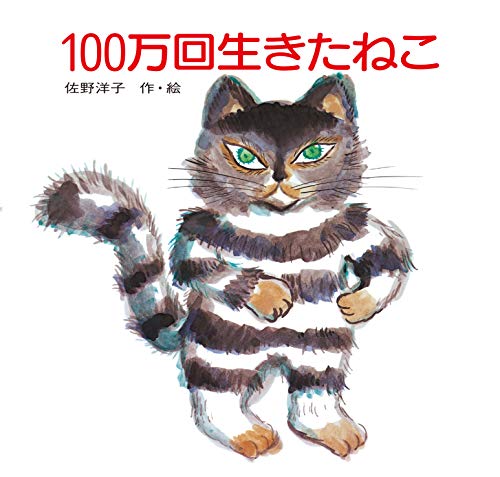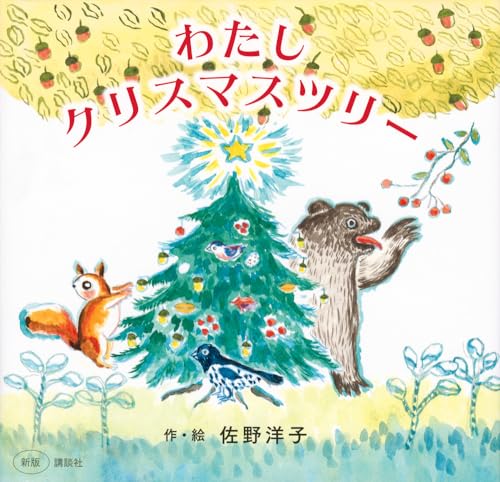『100万回生きたねこ』という絵本をご存知でしょうか?
初出は1977年と古いのですが、有名な絵本で未だに大人気です。母親が絵本好きで、私がもう高校生にもなるくらいの頃に買ってきました。
当時は私も読ませてもらって、それなりに感動した記憶。
時は経て、私にも子供が生まれ、本記事執筆時4歳。ねこちゃんが大好きなので、帰省中にせっかくなので読み聞かせてみることにしました。
・・・が、先に自分だけでザっと内容を見返してから読み聞かせるべきでした( ;∀;)
子供にとってはちょっと難しすぎるお話だったみたいです。
子供の素直な反応を書きますので、この絵本が気になっている方はご参考にどうぞ!
『100万回生きたねこ』とは、どんな絵本か(著者とあらすじ)
作・絵とも、佐野洋子さんという方です。絵本作家、エッセイイスト。
Amazonに作品一覧、著者略歴のページがあります。
『100万回生きたねこ』がすごく有名なので知らなかったのですが、他にも絵本を何冊か出されているんですね。
さて、『100万回生きたねこ』のあらすじです。多少ネタバレになりますが、ご参考に。
読んでからのお楽しみにしたい方は読み飛ばしてね。私がザックリまとめました。
― あらすじ ―
100万回も死んで、100万回も生きたねこがいました。あるときは王さまのねこ、あるときは船のりのねこ。死んではまた別のところで生き返り、死ぬことなんてへっちゃらでした。
あるとき、ねこは飼い猫ではなく、のらねことして自由に生きていました。
そこで、白いメスねこに出逢います。最初は100万回生きたことを自慢し、白いねこの気を引こうとします。でも、見向きもされず。
やがて、自慢することをやめ、白いねこといつまでも一緒にいたいと願うようになります。
時は経ち、子猫たちが生まれ育ち、巣立ち、また白いねこと二人(匹)きりに。白いねこはおばあさんになり、そして・・・。
これまで死をなんとも思わず、100万回も死んでそして生き返ってきたねこは、このあとどうなったのか。それは、絵本を読んでね。
前半部分のねこが死ぬ描写で、子供はどんどん表情を曇らせる
さて、いざ読み聞かせをしてみたときの子供の反応です。
前半部分は、ねこが誰の飼い猫でどんな風に死んでしまったのか、なんと6回も書かれています。
戦争で矢が当たったり、溺死したり、かみ殺されたり・・・。
しかも、けっこう文章量があります。こんな感じ。↓
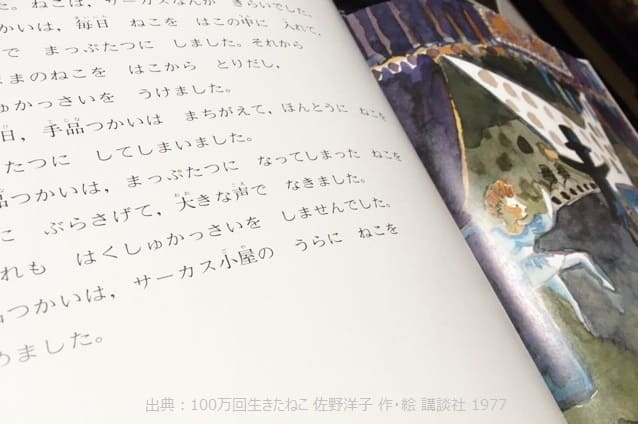
最初は悲しそうな、泣きそうな表情を浮かべ、「えー」とか声を出していました。
が、ねこが4回死に、5回死に・・・子供がどんどん表情を曇らせ・・・というか無表情になっていく。
どんどん早口になる私( ;∀;)6回目には完全に下を向き、言葉を発さない我が子・・・。
後半部分の白いねことのやりとり、描写は理解ができなかった様子
後半は雰囲気がガラッと変わります。モテモテな野良となり、自由気ままに生きるねこ。つれない白いメスねこの登場。
物語が終盤に近付くにつれ、どんどん平凡になる日々を描くストーリー構成。
前半はねこが死んでばかり。後半は大きな変化なく淡々と進むので、子供には面白くないお話だったのかもしれません・・・。
読み聞かせ終わったあとの子供の第一声は、
「なんじゃこの絵本は・・・」
でした・・・。で、ですよね・・・(*_*;
大人にとっては、胸が熱くなる物語
でもね、読み聞かせてる私の方はというと、後半は涙が出てきそうになるのを必死で我慢していたんです。
いやまあ、泣いちゃっても良かったんだけどね、別にf(^_^;
高校生くらいのときに一度読んで、「それなりに感動した」というのは間違いない。
ただ、あのときとはやっぱり違うんだよね。自分も親となって、大切な人がそばにいて、子供が成長していって。
大切な人たちと一緒に、平凡でもいいから平和に、できるだけ長く幸せに生きたい・・・という思いに改めて気づかされたんですよね。
大人になって、あらゆる大切なもの、守りたいもの、失いたくないものができてきた人が読んだときに、グッとくる絵本だなと思いました。
ある意味、絵本の前半部分というのは、まだ大切なものがよく分かっていない若者時代の暗喩のように感じました。(あくまで私の解釈ね)
子供が大人になり、ふと思い出してもう一度読んでくれたらいいなと思う(最後に)
結果的に、4歳の我が子には大変複雑な気持ちにさせた絵本でした。
もしかしたら、あともう1年・・・いや2年後なら、違った反応を見せたかもしれない。
その頃にはもう、読み聞かせは卒業してるかもしれないけど(^_^;
でも、今回この絵本を読んだことを後悔してる訳じゃなく。
将来、子供が大人になったときに、記憶の片隅に残ってくれてたらいいなと。そのときに改めて、この絵本を読んで何かを感じてくれたらいいな、と思った一冊でした。
いい絵本は、こうして親から子へと思いを繋げていけるものなんだ、と思います。ぜひ、手に取ってみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【書影の利用に関して】絵本をご紹介いただくにあたって│講談社絵本通信
https://www.akaeho.net/kikansha-yaemon/